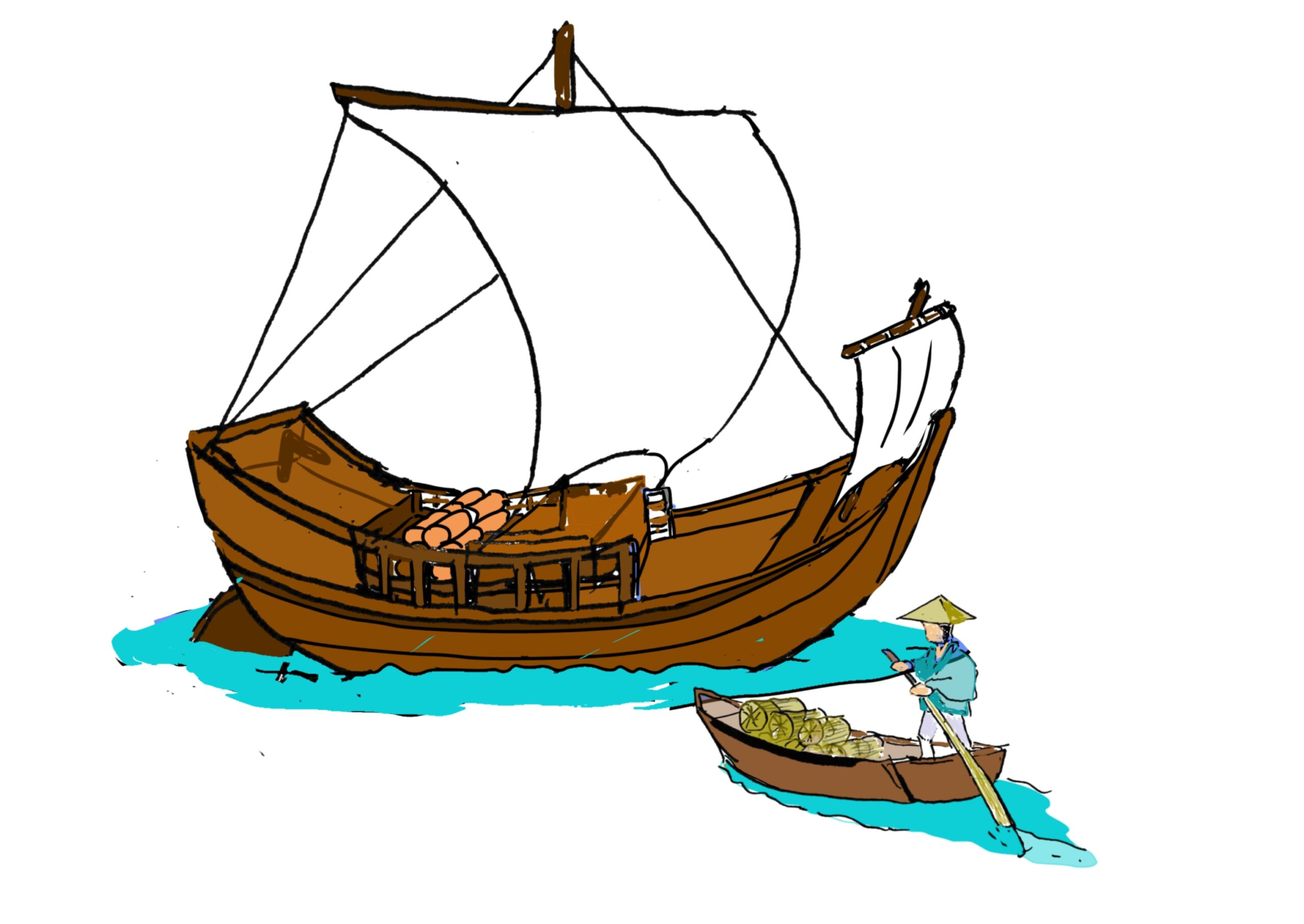江戸時代に海運が発達
大坂と江戸を結ぶ南海路
酒井と大阪を結ぶ西廻り航路
酒井と江戸を結ぶ東廻り航路
なぜ海運が発達したのか
わかりやすく、解説していきます。
キーワード
・南海路
・菱垣廻船
・西廻り航路
・東廻り航路
・北前船
江戸時代の海運の発達
① 海運の発達

商品をA地点からB地点へ運ぶとします。
この時にA地点とB地点が近ければ問題はありません。人力で持って行けます
しかし、大阪と江戸のように遠いと人力だと難しいです。
「馬」「人」「船」
3つの内、江戸時代で一番速く運べるのは?
「船」です。
一番多く運べるのは?
「船」です。
船が一番速く、一番多く運べるため江戸時代は「海運が発達」しました。
② 南海路
大阪、京都を「上方」といいます。
大阪では商売が盛ん。
京都では手工業が盛んでした。
上方で作られた物は江戸で人気がありました。
そのため、上方から江戸に大量に物が運ばれました。
大阪から江戸を結ぶ海運を「南海路」といいます。
大阪を起点に船を使い大消費地の江戸へ運ぶ海路のこと
上方からは上質な物が運ばれ「くだりもの」と呼ばれました。
一方、江戸からは上方に送られる物は品質が悪かったです。
そのため、江戸から上方に送られる物を「くだらないもの」と言われました。
現在でも使われる言葉です。
③ 菱垣廻船
菱垣廻船とは、大阪と江戸の間を行き来する船です。
木綿や醤油・油・酒・酢・紙などの日用品を大阪から江戸へ送っていました。
菱垣廻船がレースになることがあります。
その年に上方でとれた綿を江戸に送る船のことです。
菱垣廻船は大阪の安治川河口をスタートし、浦賀がゴールです。
どの船が一番速く到着することができるのか。
商人たちの威信をかけたレースでした。
通常100時間かかるところを50時間を切ってゴールをした船もいました。
④ 西廻り航路
大阪には各藩の蔵屋敷がありました。
各藩の年貢米や特産品を販売したりする倉庫
大阪の蔵屋敷まで年貢米や特産品を運びます。
一番速く、大量に運べるのは「船」です。
山形県の「酒井」から「大阪」を結ぶ航路ができました。
「西廻り航路」です。
酒井から下関を通り大阪を結ぶ航路
西廻り航路では
佐渡(新潟)⇒能登(石川)⇒兵庫⇒石見(島根)⇒下関⇒大坂
年貢米や特産品が運ばれます。
各地で各藩の年貢米や特産品を積んでいき、大阪の蔵屋敷へ運びます。
⑤ 東廻り航路
江戸は当時の大消費地です。
山形の酒井から江戸を目指す航路も整備されました。
「東廻り航路」です。
酒井から津軽海峡を通り、江戸に行く航路
大消費地の江戸まで運びたい、という思いはあるのですが、東廻り航路は西廻り航路よりも発達しませんでした。
理由は、太平洋で黒潮の流れと逆行して進まなければなりません。
そのため、危険が大きかったです。
そのため、西廻り航路の方が発展しました。
⑥ 北前船
西廻り航路では「北前船」が往復していました。
蝦夷地の小樽や函館を出発し西廻り航路を通りこんぶやにしんなどを大阪まで運ぶ船
蝦夷地なら東廻り航路を使った方が良さそうですが、安全な西廻り航路が使われました。
まとめ
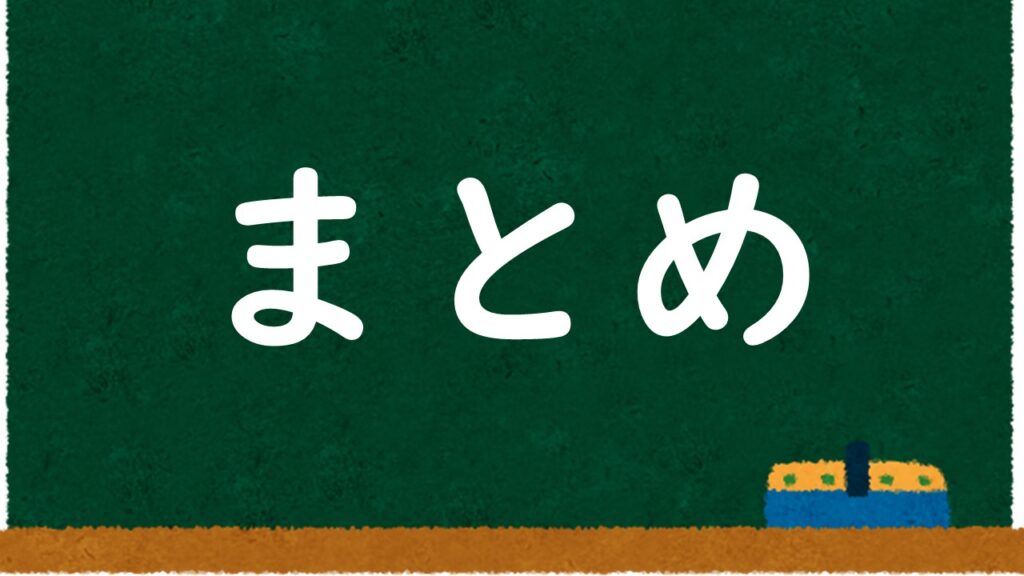
用語確認 一問一答
① 江戸と大坂を結ぶ海運
② 山形県の酒井から下関を通り大阪へ行く航路
③ 酒井から津軽海峡を通り江戸へ行く航路
用語確認 一問一答 ~答え~
① 南海路
② 西廻り航路
③ 東廻り航路