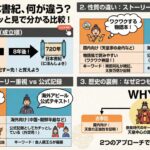701年
大宝律令が制定した
大宝律令が制定されたことで
律令国家となった
大宝律令とは
律令国家とは
わかりやすく、簡単に解説していきます。
キーワード
・大宝律令・律令国家・貴族・国司・郡司
大宝律令~律令国家~
① 大宝律令
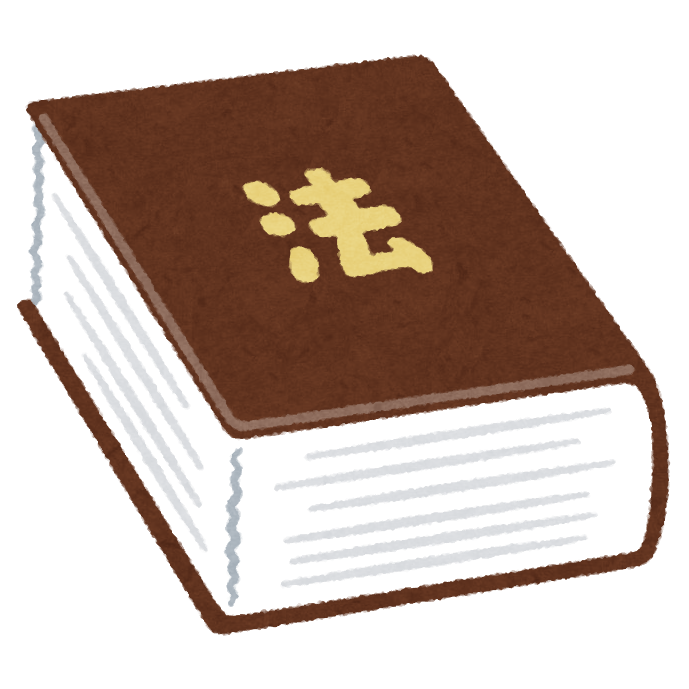
701年
唐の律令にならって「大宝律令」が制定されました。
「大宝」は元号です。
「律令」について
「律」とは刑罰の決まり
「令」とは政治をする上での決まり
現在の法律のようなものです。
律令に基づいて政治を行う国を「律令国家」といいます。
701年 唐の律令にならってつくられた刑罰や政治の決まり
律令に基づいて政治を行う国
② 国の仕組み

律令国家では天皇の命令が伝わる仕組みになっていました。
「天皇中心の政治」を行うためです。
天皇の命令は「太政官」に伝えられます。政治の中心となる中央の役所です。
太政官から八省に伝えられます。
八省とは「宮内省」「大蔵省」「刑部省」「兵部省」「民部省」「治部省」「式部省」「中務省」です。
現在の政治の仕組みと似ています。
トップの命令を各省が実行します。
中央の役所で働く人々は「貴族」とよばれます。
貴族だけでは足りずに、身分の低い人たちとも仕事をしていました。
② 地方の仕組み

天皇の命令が地方にまで行き届く仕組みになっていました。
まず、地方は多くの「国」に分けられます。
「国」という名前ですが、現在の「都道府県」だと思ってください。
国には「国府」という役所があります。
国府には都から「国司」が派遣されます。
国司が国の政治を行います。
都から派遣されているので、天皇の命令通りに動きます。
国の下に「郡」とよばれる地方組織があります。現在の市町村と思ってください。
郡の政治を行うのに、地方の豪族が「郡司」に任命されます。
国司の命令を受けて郡司が地方の政治を行います。
郡の下に「里」があります。現在の町内会の大きい物だと思ってください。
里の政治を行うのが「里長」です。
国司の命令を受けた郡司の命令を里長が実行します。
天皇中心の政治が地方の隅々まで行き渡る仕組みができます。
700年代の奈良時代にこの仕組みが完成していたことが驚きです。
③ 大宰府と多賀城
地方の役所の中で重要な役割を与えられたところがあります。
九州の「大宰府」です。
白村江の戦いで負けた後に、唐・新羅が攻めてくる心配がありました。
そのため、水城・大野城を建設したり、防人をおいたりします。
西日本の防衛と政治の中心としておかれたのが「大宰府」です。
東北の「多賀城」も特別な役割がありました。
東北地方に蝦夷と呼ばれる人々がいました。
この人たちは、政府の言うことをきかない人が多かったです。
東北地方の政治や軍事を担当させる「多賀城」を置き、東北地方ににらみをきかせます。
まとめ
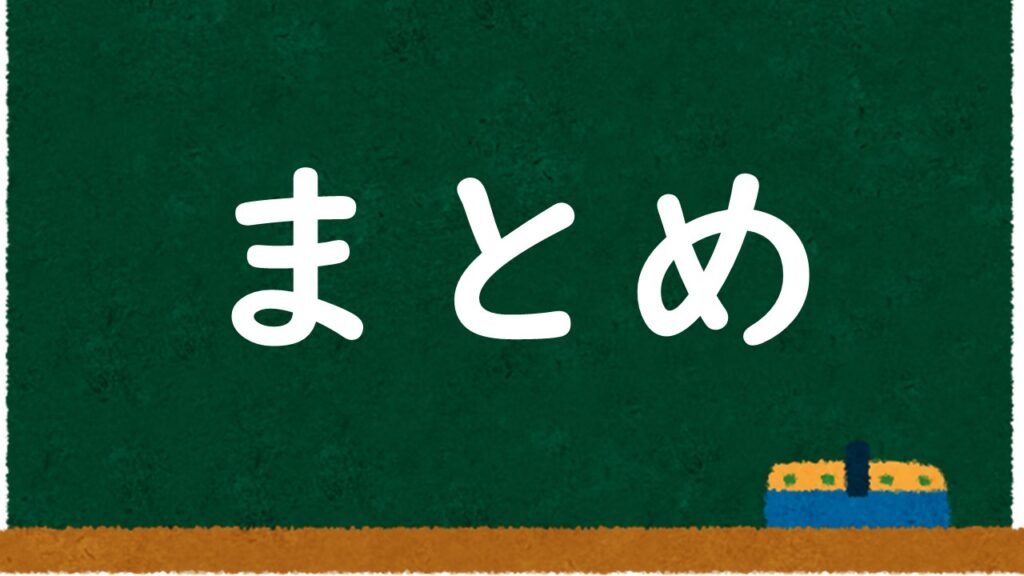
用語確認 一問一答
① 701年に唐の律令にならって制定されたもの
② 律令によって政治を行う国家
③ 都から派遣され地方組織の国の政治を行った役職
④ 九州地方の政治や防衛にあたった機関
⑤ 東北地方の政治や防衛にあたった機関