710年
唐の長安にならった都をつくった
平城京
奈良時代がはじまった
平城京とは
わかりやすく、簡単に解説していきます。
キーワード
・平城京
・奈良時代
・和同開珎
平城京

① 平城京に遷都
710年に都を移しました。
710年 なんと立派な「平城京」です。
710年の平城京に都を移してから「奈良時代」がはじまります。
平城京とはどのような都だったのか。
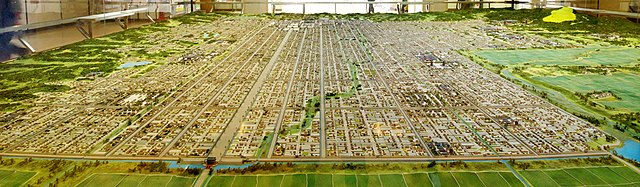
平城京の復元模型を見るとどのような都だったのか分かります。
唐の都の「長安」と同じような形にします。
道が東西に真っ直ぐ、南北に真っ直ぐ延びています。
「碁盤の目のよう」と表現されます。
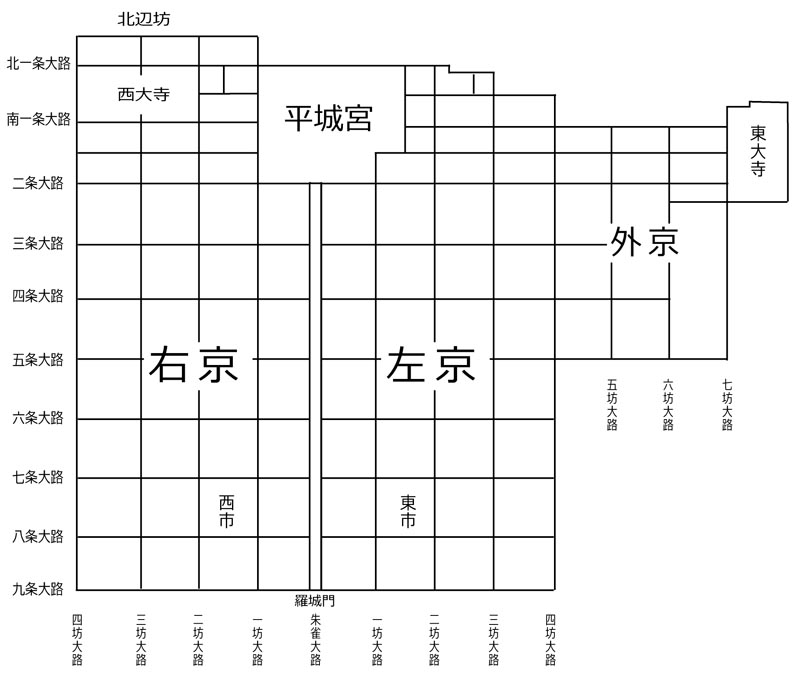
北に「平城宮」があります。
ここに天皇が住んでいます。
天皇の住まいだけでなく、朝廷(天皇のまわりで政治を行う)が政治を行っていました。
平城京を見て「おかなしいなぁ?」と思うところがあります。
「右京」と「左京」が反対になっています。
天皇の住まいの平城宮から平城京を見ました。
すると「天皇から見ると、右京と左京があっている」ことが分かります。
「天皇中心の都づくり」のあらわれです。
平城京を見ると「市」があります。
市では様々な物が売られていました。
買うためには、お金も必要です。
「和同開珎」が平城京では流通していました。
全国でどれだけ流通していたかは分かりません。
しかし、日本で最初の貨幣だと言われています。
② 全ての道は平城京へ
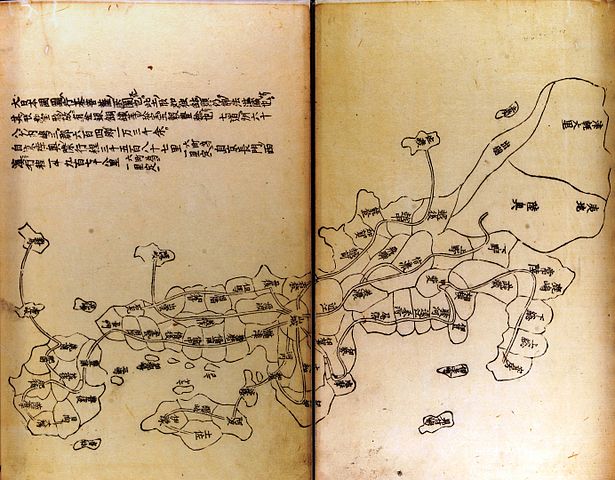
道の整備がされました。
九州地方にいても
東北地方にいても
平城京に行けるように道が整備されます。
すべて道は「平城京」にいる「天皇」につながるようになっています。
「天皇中心の国づくり」です。
まとめ
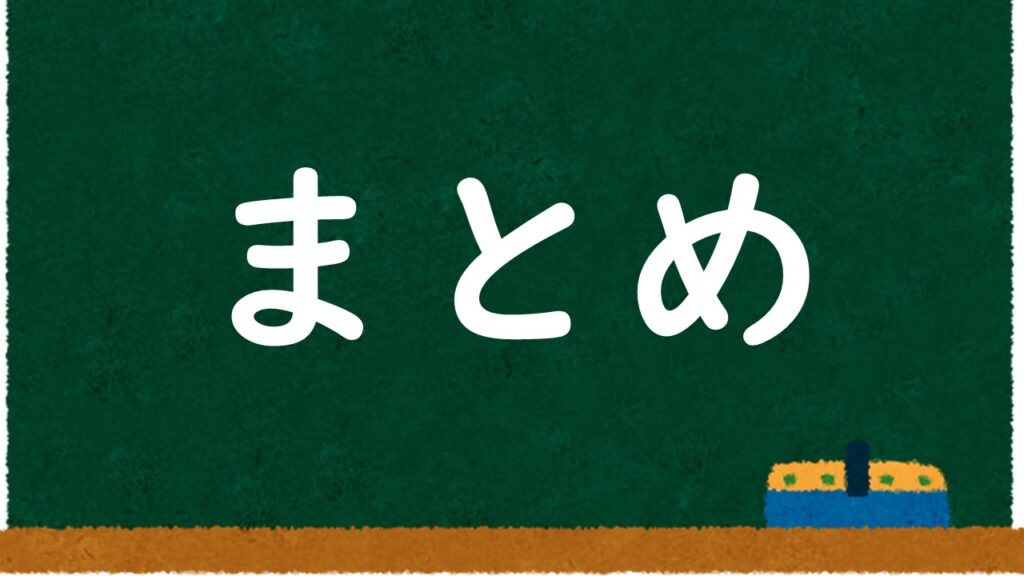
用語確認 一問一答
① 710年から日本の都の名前
② 平城京に都がある時代
③ 平城京で流通していた貨幣
用語確認 一問一答 ~答え~
① 平城京
② 奈良時代
③ 和同開珎

