「インドへ行くために、喜望峰を通った冒険家は誰?」
「バスコ・ダ・ガマって何をした人なの?」
この記事では、大航海時代にヨーロッパからインドへの航路を切り開いたポルトガルの探検家、バスコ・ダ・ガマについて中学生向けにわかりやすく紹介します!授業で扱った「香辛料」や「イスラム教との関係」もふまえて、地図で世界が変わった瞬間を見てみましょう!
バスコ・ダ・ガマ
1. なぜインドへ行きたかったのか?
理由:香辛料(こしょう・シナモンなど)
- ヨーロッパでは肉料理が中心 → 味つけに必要!
- 腐った肉のにおい消しに使える
- 薬としても利用されていた
→ 高価な商品で、貴族や王様もほしがる!
2. 陸路が使えない理由は?
陸地を通るにはイスラム教の国を越える必要があった!
| 国 | 宗教 | ヨーロッパから見て |
|---|---|---|
| オスマン帝国 | イスラム教 | 十字軍の影響で、通りにくかった |
| ムガル帝国 | イスラム教 | 東南アジアとの関係も深かった |
キリスト教とイスラム教の対立の影響で、陸路は封じられていた
3. バスコ・ダ・ガマの航海!
国:ポルトガル
航路:ヨーロッパ → 喜望峰(アフリカ南端) → インド
| 地点 | 意味 |
|---|---|
| 喜望峰(アフリカ南端) | これを越えればインドに近づける地点 |
| インド到達 | 香辛料の直接入手に成功! |
| 帰国 | ポルトガルの貿易と地位を大きく高めた |
「海の旅に必要なもの」として
→ 食料・水・仲間・技術・羅針盤・地図などがあった
羅針盤・地図の開発で海に出られる時代 大航海時代のスタート!
キーワードまとめ
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| バスコ・ダ・ガマ | 喜望峰を通って東回りでインドに到達したポルトガルの探検家 |
| 香辛料 | ヨーロッパで人気だったスパイス。腐りかけの肉にも使えた |
| 喜望峰 | アフリカの南端。インドへの海のルートの重要ポイント |
| オスマン帝国 | イスラム教の大国。キリスト教のヨーロッパと対立していた |
| 大航海時代 | 陸路の制限を海で乗り越え、世界の航路が広がった時代 |
確認問題
確認問題(選択式)
- バスコ・ダ・ガマがたどった航路として正しいのは?
A. ヨーロッパ → 北極 → アメリカ
B. ヨーロッパ → 喜望峰 → インド
C. ヨーロッパ → 南アメリカ → インド
D. ヨーロッパ → 中東 → インド - 香辛料が人気だった理由に当てはまらないものは?
A. 味つけになる B. 肉を腐らせる C. においをごまかす D. 薬として使える - バスコ・ダ・ガマの国は?
A. スペイン B. イギリス C. フランス D. ポルトガル - 陸路でインドに行けなかった理由は?
A. オスマン帝国やムガル帝国の宗教対立 B. 地図がなかったから
C. 船がなかったから D. 気候が寒かったから - バスコ・ダ・ガマの航海が成功したことで起きたこととして正しいのは?
A. ポルトガルがインドの宗教を変えた B. 貿易の中心が日本になった
C. 香辛料が直接手に入るようになった D. アメリカの発見につながった
✅ 答え(記号+内容)
- B:ヨーロッパ → 喜望峰 → インド
- B:肉を腐らせる
- D:ポルトガル
- A:オスマン帝国やムガル帝国の宗教対立
- C:香辛料が直接手に入るようになった
記述練習問題
- バスコ・ダ・ガマがインドへ向かうために選んだ航路と、その理由を説明しなさい。
- なぜ陸路ではインドに行けなかったのか、宗教や歴史の関係から説明しなさい。
- バスコ・ダ・ガマの航海がポルトガルにどんな影響を与えたか、あなたの言葉で書きなさい。
✅ 解答例
1. バスコ・ダ・ガマはヨーロッパからアフリカの南端「喜望峰」を通ってインドへ向かう航路を選びました。陸地を通るよりも宗教の対立を避けられ、海なら通りやすかったからです。
2. 当時の陸路にはイスラム教のオスマン帝国やムガル帝国があり、キリスト教との対立でヨーロッパの人が通るのがむずかしかった。そのため、安全に香辛料を手に入れるには海から行くしかなかった。
3. バスコ・ダ・ガマの航海が成功したことで、ポルトガルは香辛料を直接手に入れることができ、貿易で大きな利益を得ました。その結果、ポルトガルは世界で重要な国の一つになったと思います。

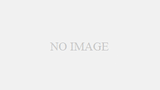
コメント