江戸時代の身分は主に武士、百姓、町人に分けらました。
それぞれどのような特権や暮らしぶりだったのか。
江戸時代の身分とは
武士とは 百姓とは 町人とは
わかりやすく解説していきます。
キーワード
・武士
・百姓
・町人
・五人組
江戸時代の身分~武士~

武士は人口の割合の7%しかいません。
特権階級です。
特権が主に3つありました。
① 名字を公に名乗る
② 刀を日常的に差すこと(帯刀)
③ 切り捨てごめん
右の絵を見ると武士の特権が分かります。
武士のイラストでも帯刀をしています
③の切り捨てごめんとは、武士は百姓や町人を事情があれば刀で切って良いというルールです。
さすが特権階級。
しかし、切り捨てた後にしなければならないことがありました。
役所に切った場所や理由を伝える必要がありました。斬り捨てごめんにも事務手続きが必要です。
江戸時代の身分~町人~
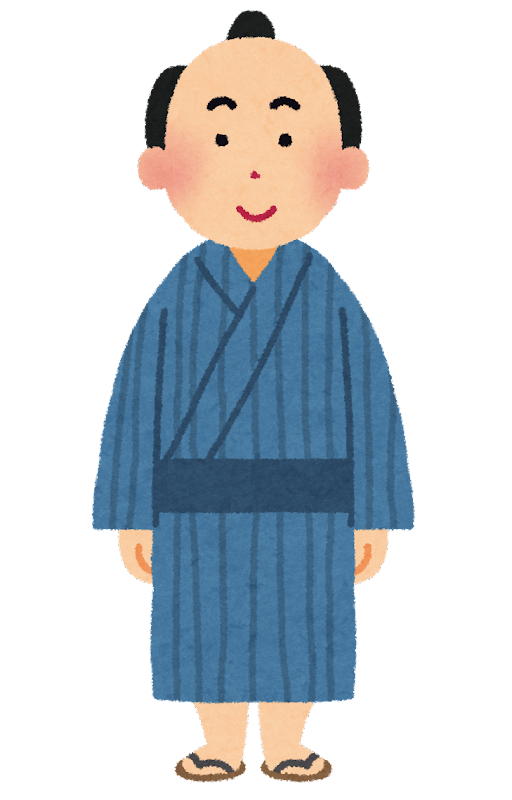
町人は人口の5%です。
武士より少ない割合です。意外です。
町人は商人と職人に分けられます。
商人は商売をする人
職人は手に職をつけている人
町人は「町役人」という人たちがいました。
町役人を中心に町の自治を行っていました。町の運営に参加できるのは、地主や家を持っている人に限られていました。
住み込みで仕事を覚える若い町人。借りた家で商売をする町人。
町人の中でもヒエラルキーがあります。
江戸時代の身分~百姓~

百姓は全人口の85%です。
江戸時代のほとんどの人が百姓です。
百姓について徳川家康がいったとされる言葉が残されています。
「百姓は、死なぬように年貢をとれ」
簡単に言うと、「百姓の仕事は年貢を納めること」だ!
江戸時代は年貢を納めます。
五公五民と言われる「年貢率が50%」です。
現在で考えると年収が「500万円」だと税金が「250万円」のイメージです。
江戸時代の百姓の厳しさが伝わります。
江戸時代は年貢以外にも負担がありました。特産物に税がかけられていました。
江戸時代は、土木工事の負担もありました。
百姓には、「こういった生活をしなさい」という百姓の心得がありました。
- 酒や茶を買って飲まないこと。
- 栗や粟を食べ、米を多く食べないこと。
- 麻と木綿のほかは着てはいけない。
- 早起きをし、朝は草を刈り、昼は田畑を耕作し、夜は縄を綯い、俵を編むなど、仕事を行うこと。
一生守るのは難しそうです。

どうして、わざわざこんなルールを出したのだろう?
百姓の心得が出されたり理由を考える前に、
ルールは守られているから出されるのか?
守られていないから出されるのか?
これは「ルールが守られていないから」です。
そう考えると、江戸時代の百姓の暮らしは裕福な人もいたのかもしれません。
五人組 連帯組織を負わせる
江戸幕府は百姓同士で「五人組」と呼ばれる組織をつくらせました。
連帯責任を負う仕組みです。
1人が犯罪をすると他の4人も罰せられます。
そうすると犯罪に手を染めないだろうという考えでつくられました。
年貢も五人組で連帯組織を負います。
農村の仕組み
江戸時代の農村の仕組みです。
有力な百姓が村役人として庄屋、組頭、百姓代になります。
村役人が村の自治を行います。町内会長みたいな人です。
土地を持つ本百姓
土地を持たない水のみ百姓
に分けられます。
百姓の世界にもヒエラルキーがありました。
用語確認 一問一答
① 江戸時代の人口の約7%の特権階級
② 江戸時代の人口の約5%で商人、職人からなる身分
③ 江戸時代の人口の約85%で年貢を納めることが仕事の身分
④ 百姓が年貢の納入や犯罪で連帯責任を負う仕組み
用語確認 一問一答 ~答え~
① 武士
② 町人
③ 百姓
④ 五人組

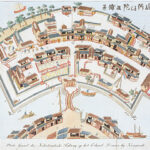


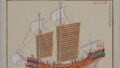
コメント