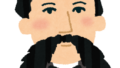大日本帝国憲法の発布までの流れと発布後の流れです。
1889年 アジア初の憲法である「大日本帝国憲法」が発布されます。
伊藤博文~ヨーロッパの憲法に学ぶ~
大久保利通が暗殺された政府。
中心人物は「伊藤博文」
憲法を作る中心人物も「伊藤博文」
伊藤博文は憲法を作るために、ヨーロッパを訪問します。
憲法作成時に最も参考にした国は「ドイツ」です。
ドイツには皇帝がいました。
皇帝の権限が強い憲法を作っていました。
難しく言うと、ドイツは「君主権が強い憲法」です。
「ドイツの皇帝」を「日本は天皇」に変えて、「君主権が強い憲法を作ろう」と考えます。だから、ドイツの憲法を参考にしました。
内閣制度~初代内閣総理大臣 伊藤博文~
伊藤博文は憲法を作る前に、内閣制度を作ります。
内閣制度は内閣総理大臣をトップとした天皇を助ける仕事です。
初代内閣総理大臣には伊藤博文が就任しました。
大日本帝国憲法の発布~アジア初の憲法~
1889年に「大日本帝国憲法」は発布されました。
大日本帝国憲法は言葉が難しいので、現代語訳になっています。
| 第1条 大日本帝国は、永遠に続く同じ家系の天皇が治める。 第3条 天皇は、神のように尊い存在であり、汚してはならない。 第4条 天皇は、国の元首であり、国や国民を治める権利を持つ。 第5条 天皇は、国会の意見を取り入れながら、法律を定める権利を持つ。 第11条 天皇は、陸海軍を統率する 第20条 日本臣民(天皇の支配対象となる国民)は、法律の定めるところに従い、兵役の義務を有する。 第29条 日本臣民(天皇の支配対象となる国民)は法律に定められた範囲内で、言論、著作、出版、集会、団体をつくることの自由を持つ。 ※ 制限はあったが、国民の権利が一部認められた |
「天皇」という言葉が多いことが分かります。
天皇は主権者で元首です。国の政治や軍隊を動かすことが可能です。
国民は臣民とされ、憲法の範囲内で自由が認められました。
大日本帝国憲法の発布により、不平等条約改正の外国との交渉がしやすくなります。
岩倉使節団の時、条約改正を求めても法の整備が徹底されていなくて、交渉が上手くいきませんでした。
大日本帝国憲法ができたことによって、不平等条約である、相手国に領事裁判権を認めること、日本に関税自主権がないことの撤廃の交渉が進むようになっていきます。
帝国議会
憲法の中で「帝国議会」が作られました。
帝国議会は選挙で選ばれた「衆議院」
天皇が指名する「貴族院」
の2つの院からなる二院制が採用されました。
日本で初めての選挙
憲法ができた翌年の1890年に衆議院の選挙が行われました。
帝国議会の第1回衆議院議員選挙で選挙権があたえられた人たちです。
「直接国税を15円以上納める満25歳以上の男子」
用語確認 一問一答
① 初代内閣総理大臣になった人物
② 1889年に発布された日本の憲法
③ ②の憲法を作るときに参考にした国
④ 衆議院、貴族院からなる議会
⑤ 第1回衆議院議員選挙で選挙権が与えられた人の条件
用語確認 一問一答 ~答え~
① 伊藤博文
② 大日本帝国憲法
③ ドイツ
④ 帝国議会
⑤ 直接国税15円以上を納める満25歳以上の男子