3世紀後半
奈良県を中心に栄え
強大な力を持つ王と
有力な豪族からなる
大和政権
大和政権とは、どのようなものか
わかりやすく、簡単に解説していきます。
キーワード
・大和政権
・古墳
・前方後円墳
・大王
大和政権
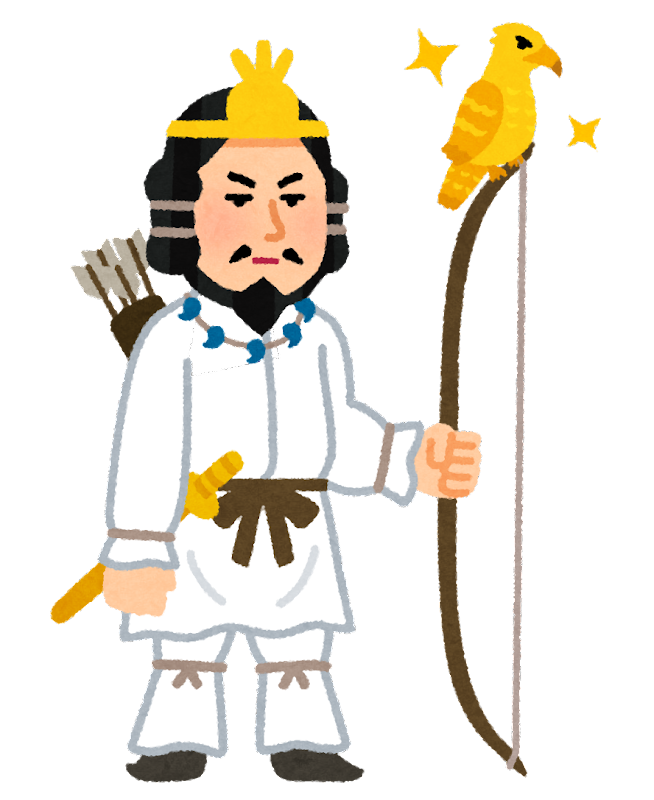
大和政権の誕生
卑弥呼の邪馬台国の後
近畿地方の奈良盆地を中心とする政権ができました。
大きな力を持つ「王」
王に従う「有力な豪族」で組織されます。
これを「大和政権」と言います。
3世紀後半に奈良盆地を中心に強力な王と有力な豪族から組織された
② 古墳
大和政権は多くの前方後円墳を造りました。
四角の「方」と呼ばれる部分と「円」の部分があり「前方後円墳」と呼ばれる形です。
カギ穴のような形の古墳です。
有名なものは大阪府にある「大仙古墳」です。
大仙古墳
制作期間 15年
関わった人 600万人以上
総工事費 800億円以上

どうしてこれほど大きな古墳を造ったのかな?
キーワードは「お墓」「権力」「力を示す」です。
昼は人が造り、夜は神が造った
と言われるものをつくり、権力を示したのだと言われています。
③ 大王の誕生
前方後円墳の分布は、最初は「近畿地方」が多いです。
段々と九州地方から東北地方へと広がっていきます。
前方後円墳の分布から
大和政権の勢力が九州地方から東北地方まで広がっていた
ことが分かります。
5世紀後半になると
大和政権の「王」は「大王」と呼ばれるようになります。
大王の1人である「ワカタケル大王」
「ワカタケル大王」と書かれた鉄剣が見つかります。
埼玉県の稲荷山古墳
熊本県の江田船山古墳
から発見されました。
つまり、
ワカタケル大王の勢力範囲が少なくとも埼玉県から熊本県までおよんでいた
ことが分かります。
「前方後円墳の分布」と「ワカタケル大王の鉄剣」から大和政権が日本を納めていたことが分かります。
まとめ
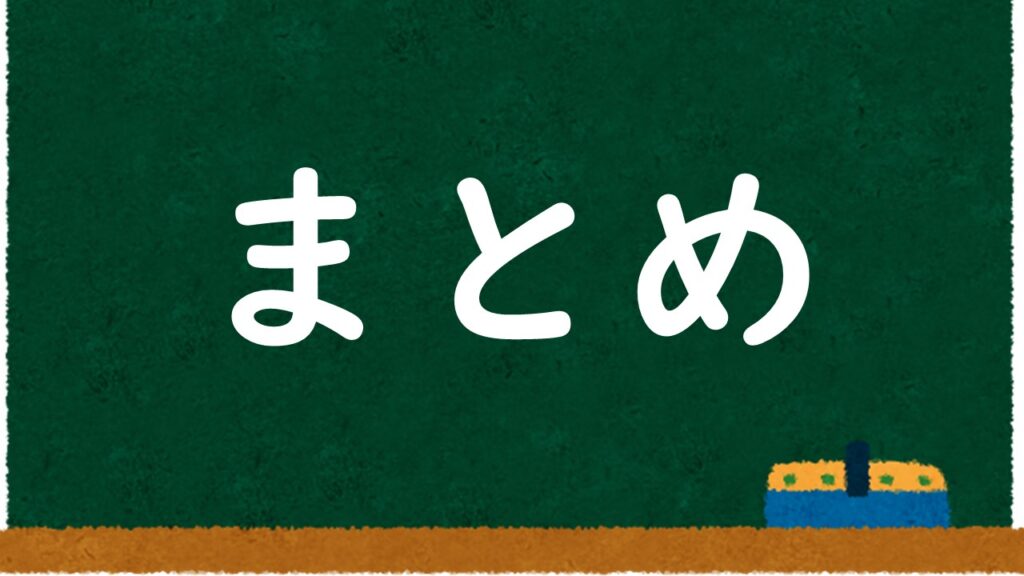
用語確認 一問一答
① 3世紀後半に奈良盆地を中心に栄えた政権
② 大和政権が造らせたカギ穴のような形の古墳
③ 5世紀後半頃からの大和政権の王の呼ばれ方
用語確認 一問一答 ~答え~
① 大和政権
② 前方後円墳
③ 大王

