縄文時代とは
どんな時代なのか
道具は何を使って
食べ物は何を食べて
住居はどんなものに住んでいた
縄文時代の特徴を
わかりやすく、簡単に解説していきます。
キーワード
・縄文時代
・縄文土器
・貝塚
・土偶
・たて穴住居
縄文時代
① 縄文時代の生活
縄文時代と言っても、2万年続いた時代です。
どのような特徴があるか
縄文時代は狩猟と採集の生活を送っていました。
狩猟で鹿、いのしし、鳥などを捕っていました。
採集でどんぐり、栗などの木の実をとっていました。
それを小さな村で分けて食べていました。
② 縄文時代の道具
縄文土器

縄文時代に使われていた土器
「縄文土器」です。
縄文土器には、表面に縄目の文様がありました。この縄目の文様から「縄文時代」といわれます。
国褐色をした表面に縄目の文様がつけられた土器
貝塚

縄文時代は「貝塚」とよばれるものがありました。
貝塚は、貝殻や魚の骨などを捨てた場所です
貝殻や魚の骨などを捨てた場所
貝塚はゴミ捨て場一種だと考えられていました。
しかし、縄文時代の人はすべてのものに霊がいるとされていました。
アニミズムといいます。
貝塚は会や魚を供養(くよう)したのではないかとも考えられています。
土偶

出典:Wikipedia
土偶がつくられます。
土偶は豊作をお祈りしたり、お祭りの時に使われたりしました。
土偶が壊れているものが多いのは、土偶の破片をばらまいてお祈りをしたからだと言われています。
縄文時代は神秘的です。
③ 縄文時代の食べ物
縄文時代は狩猟と採集の時代です。
狩猟で獲れた鹿、いのしし、鳥などを食べていました。
海で漁が行われ、くじらやさけ、ますなどを食べていました。
貝もとれたので、貝も食べます。
採集では、くり、どんぐり、きのこなどを採って食べていました。
木の実などのは生では食べられません。縄文土器の出番です。
縄文土器で煮ることができて、渋みをとばすことができました。
どんぐりでクッキーを作っていました。
季節ごとに食べられる物が違い、とれるものを食べて生活を送ります。
④ 縄文時代の住居

出典:Wikipedia
縄文時代の住居は「たて穴住居」です。
地面をほりさげて、柱をたてて屋根をかけてつくっていました。
中は広々としていますが、10畳程度です。
火をたくところで、縄文土器で食べ物を煮ていたことがイメージできます。
火をたくことで寒さ対策にもなります。
しかも、下は地面です。
私たちが住むにはあまり居心地の良いものではないです。
しかし、縄文時代では十分に住める建物でした。
まとめ
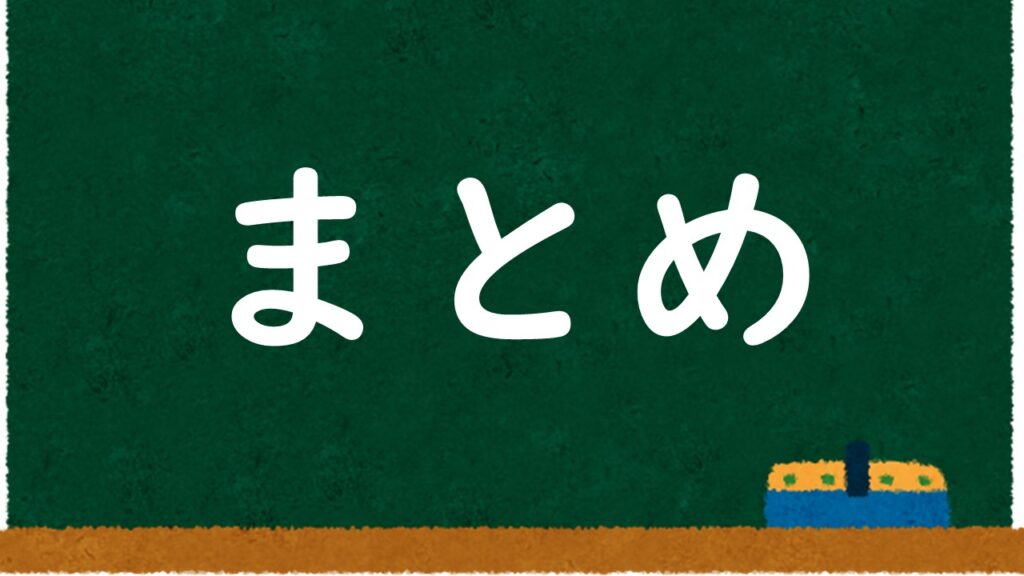
用語確認 一問一答
① 土器の表面に縄目の文様がある土器
② 縄文土器を使っていた時代
③ 魚の骨や貝殻を捨てた場所
④ 縄文時代で豊作のお祈りやお祭りで使われたもの
⑤ 縄文時代の人々が住んでいた住居の名前
用語確認 一問一答 ~答え~
① 縄文土器
② 縄文時代
③ 貝塚
④ 土偶
⑤ たて穴住居


